
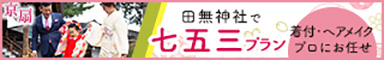





田無神社は鎌倉期の創立以来、田無の地で皆様とともにありました。日本文化の魂を宿す神社として日本の伝統文化を伝えるべく、また、地域社会との絆を深めるべく新たな試みを行っています。開かれた神社として、さまざまな祭事・イベントの様子をお伝えします。
2022年 1月 23日(日)
〜お焚き上げの注意〜
田無神社以外の神社・仏閣で、
オルゴール音が鳴る、電池入りのお守り
が頒布されているようです。
お焚き上げの際に、爆発の恐れがあり
大変危険ですので、
お守りを授かった神社・仏閣にお戻しいただくよう
お願い申し上げます。
お焚き上げ
古いお神札は、一年間お守りいただいたことに感謝申し上げてから、お神札を受けた神社のお焚き上げ処へ納めてお焚き上げをしていただき、新しいお神札をお受けします。田無神社では年間を通して、お焚き上げを受け付けております。境内東側のお神輿近くにお焚き上げ箱がありますので、お納めください。
2022年 1月 18日(火)
〜敵国降伏臨時大祭執行の札発見〜
この度、宮司家倉庫から、敵国降伏臨時大祭執行の札が発見されました。
これは、日露戦争宣戦布告(明治37年2月10日)の5日後の明治37年2月15日から3日間、「敵国降伏臨時大祭」を行う旨を当時の氏子一同に通知する標札です。
118年もの時を経ており、当時の人々が大国ロシアとの戦争に当たってご祭神の加護を祈った、その歴史の重みを感じることができます。
写真の背景に写る「日露戦没記念碑」は、日露戦争での戦勝を記念し、明治40年に教育者である刑部真琴によって建立されました。文字は日露戦争の際に元帥陸軍大将として満州軍総司令官を務めた大山巌による揮毫です。日露戦争では田無村から71人が出征し、3人が戦死、68人が凱旋帰国しました。71人の出征者のうち、70人が陸軍、1人だけが海軍です。この碑の裏には出征者の氏名が、田無小学校の初代校長・刑部真琴の発案によって彫られ、その消息を今日に伝えています。刑部真琴は田無神社兼務社の阿波洲神社拝殿に掲げられている、凱旋記念扁額にも保谷出身従軍軍人の名を刻みました。
戦利品として持ち帰った砲弾は、信管は外され、日露戦争戦没者記念碑前に納められています。
2022年 1月 5日(水)
〜神社de献血〜
1月4日(火)・1月5日(水)に
国登録有形文化財である
田無神社参集殿において
「神社de献血」献血会を実施しました。
2日間合計で
献血申込者137人
献血者119人でした。
たくさんの方に献血のご協力をいただき
誠にありがとうございました。
2021年 12月 27日(月)
〜おかえりなさいお稲荷様〜
12月27日にお稲荷様が野分初稲荷神社にお帰りになりました。
これまで傷ついていた耳や足をお直しし、元どおりの麗しいお姿を取り戻しました。
初詣で田無神社境内社「野分初稲荷神社」をご参拝ください。
2021年 12月 16日(木)
〜龍神池のかいぼり〜
龍神池をきれいな池に保つため、12月16日(木)にかいぼりを行いました。
「かいぼり」とは日本で古くから行なわれている、ため池の伝統的な管理手法です。
龍神池では池の水を抜き、天日干しを行い、底泥を乾かして水質の向上を図ります。
また、濁りの原因であるヘドロを取り除きます。ヘドロには栄養が多く含まれているので、境内にある畑に肥料として活用します。
このように、定期的に池の環境改善を行うことで、生きものが住みやすい環境を維持することができます。